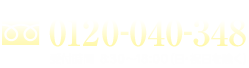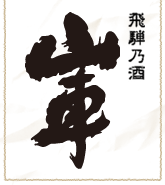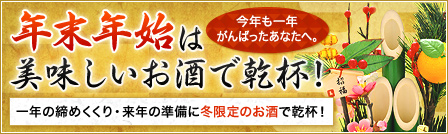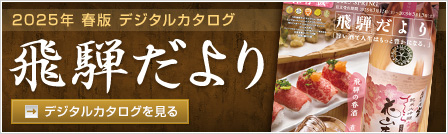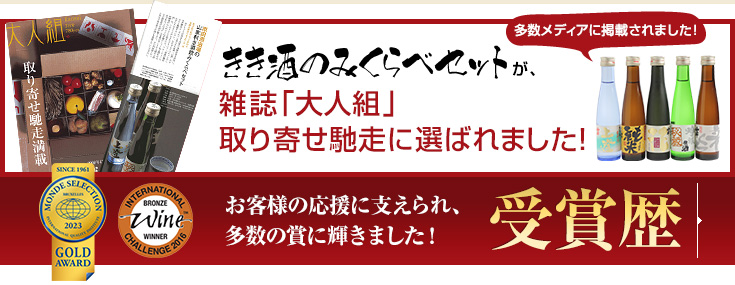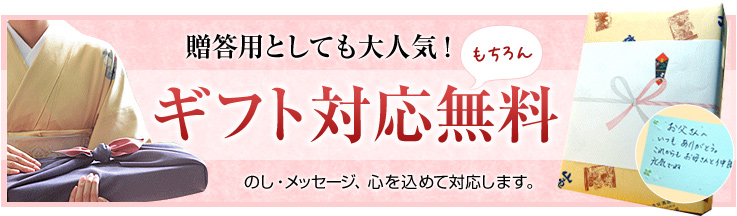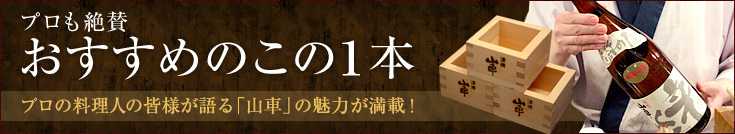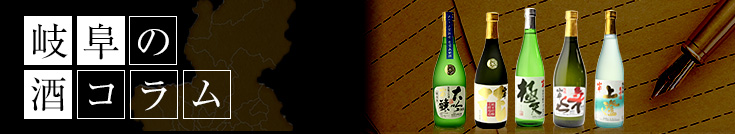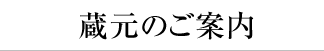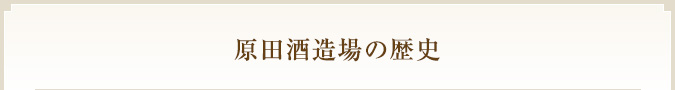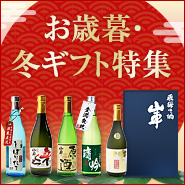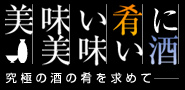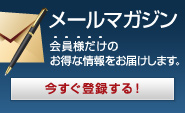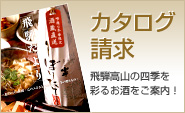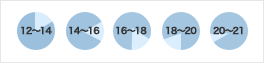- 飛騨乃酒 山車 HOME
- 岐阜の酒コラム
- 高山祭(秋祭り)|世界遺産に登録された飛騨の伝統祭事を完全解説
岐阜の酒コラム
高山祭(秋祭り)|世界遺産に登録された飛騨の伝統祭事を完全解説
こんにちは原田酒造場です。
飛騨高山が誇る伝統行事「高山祭」。春の山王祭と並ぶ二大祭りの一つ、秋の高山祭(八幡祭)は、絢爛豪華な屋台行事と幻想的な宵祭りで知られ、毎年多くの観光客を魅了しています。16世紀後半から17世紀に発祥し、2016年にはユネスコ無形文化遺産に登録されたこの伝統ある祭りの魅力を、準備段階から本番までを徹底的に解説します。
高山祭(秋祭り)とは?基本情報と見どころをご紹介
高山祭の秋祭りは、旧高山城下町北半分の氏神様である櫻山八幡宮の例祭として毎年10月9日・10日に開催される伝統行事です。正式名称を「八幡祭」と呼び、11台の豪華な屋台が町を巡る様子は、まさに秋の風物詩となっています。
開催時期と歴史的背景
江戸時代、飛騨を治めた金森氏の時代(1585年~1692年)に始まったとされる高山祭。特に屋台の起源は1718年頃とされ、以来300年以上にわたって飛騨の匠の技術と文化を今に伝えています。かつては旧暦で執り行われていましたが、現在は10月9日・10日に固定されています。
祭りまでの準備行事
秋の高山祭は、実は8月1日の「祭事始祭」から始まります。この日から年行司(その年の祭りを取り仕切る役職)による本格的な準備が開始されます。祭りの約2週間前からは、各屋台組で「屋台やわい」と呼ばれる準備作業が行われ、胴幕や御簾、装飾品の取り付けが始まります。
また、この時期になると町内では屋台囃子の練習が始まり、夜な夜な笛や太鼓の音が響き渡ります。地域の人々にとって、この音色は祭りの近づきを告げる風物詩となっています。
10月7日の夜には、八幡宮で「試楽祭」と「屋台順番抽籤祭」が執り行われ、いよいよ本番に向けた準備が大詰めを迎えます。
圧巻の勢ぞろい!11台の絢爛豪華な山車を徹底解説
高山祭最大の見どころである屋台行事。11台の豪華絢爛な屋台それぞれに、独自の特徴と長い歴史が刻まれています。
高山祭の屋台は、飛騨の匠の技術の粋を集めた芸術品です。それぞれの屋台には独自の特徴と歴史があり、国の重要有形民俗文化財に指定されています。11台の屋台を詳しくご紹介します。
神楽台(かぐらたい)
創建:宝永5年(1708年) 最古の屋台の一つである神楽台は、金森重勝(左京)から寄進された大太鼓が起源となっています。
特徴と見どころ:
- 構造:屋根無し、太鼓昇降式、四輪外御所車
- 文化12年(1815年)の大改造で現在の形に
- 棟飾り:鳳凰と三神(天照、八幡、春日)を表した金幣束が特徴
- 太鼓:音響遠近に響き渡る名器(文久年間に他組の妬みで切りつけられた逸話あり)
- 祭礼時:侍烏帽子、素襖姿の5人の楽人が乗り込み、獅子舞を伴う
歴史的改修:
- 文化改修:田中大秀設計、風井屋長右衛門工匠
- 明治改修:村山民次郎工匠
- 昭和の修理:昭和9年、昭和41年
布袋台(ほていたい)
創建年代は不詳ですが、天明年間(1781年~1789年)には既にからくり演技が行われていたとされています。
特徴と見どころ:
- 構造:切破風屋根、四輪内板車
- からくり人形:36条の手綱による精緻な操り
- からくりの内容:
- 男女2人の唐子が5本の綾(ブランコ)を渡る
- 布袋和尚の肩に乗って演技
- 布袋の軍配から「和光同塵」の幟が出現
- 建築的特徴:
- 鳥居形の出入口
- 下段上部が中段を兼ねる独特の構造
- 文化年間以来の古趣を残す
歴史的改修:
- 文化8年(1811年):現在の台形に大改修
- 工匠:古田与兵衛
- 彫刻:中川吉兵衛
- 近代の修理:大正初年、昭和35年、昭和42年
金鳳台(きんぽうたい)
創建:享保3年(1718年)という伝承があり、天明年間の曳行記録が残っています。
特徴と見どころ:
- 構造:切破風屋根、四輪内板内車
- 装飾:
- 棟飾りに台名を象徴する金地の鳳凰
- 中段欄間には四条派風の四季の草花
- 人形:神功皇后と武内宿禰(応神天皇を抱く)
- 特筆:文政再興当時の面影をよく残し、最も整備された形態を持つ
歴史的変遷:
- 文化年間:一時休台
- 文政元年(1818年):再興
- 嘉永5年(1852年):改修
- 工匠:文政再興時は古田与兵衛、嘉永改修時は角竹茂助
大八台(だいはちたい)
創建:文化年間(1804年~1818年) 高山で最初の3輪屋台として知られ、その独特な構造が特徴です。
特徴と見どころ:
- 構造:切破風屋根、三輪外御所車
- 車輪:外2輪は高山屋台中最大(直径1.56メートル)
- 装飾:
- 屋根両端に八幡、春日大神を表す大金幣束
- 中段は幕を張らない御殿風の吹き抜け構造
- 音楽:
- 屋台囃子「大八」の発祥
- 6人の童子による演奏(青、緑、桃色の直衣烏帽子姿)
歴史的改修:
- 文政創建:工匠・光賀屋清七、塗師・輪島屋儀兵衛
- 明治改修:工匠・村山民次郎
- 近代の修理:明治41年、昭和30年、昭和46年
鳩峯車(きゅうほうしゃ)
創建:延享4年(1747年)以前 当初は「大津絵」という台銘で知られていた古い屋台です。
特徴と見どころ:
- 構造:切破風屋根、三輪外御所車(天保8年から)
- 初期の特徴:
- 「外法の梯子剃り」と呼ばれる福禄寿と唐子のからくり
- 4輪から3輪への改造
- 装飾:見送り幕、胴掛けに贅沢な綴錦織を使用
歴史的変遷:
- 文政9年(1826年):大破により休台
- 天保8年(1837年):再建、台銘を「鳩峯車」に改称
- 安政年間:再度休台
- 慶応3年(1867年):修理
- 明治27年(1894年):大修理
工匠の系譜:
- 天保再建:牧野屋忠三郎・彦三郎
- 慶応改修:谷口与三郎宗之
- 明治改修:村山民次郎
- 神馬台(じんまたい)
神馬台(じんまたい)
創建:享保3年(1718年) 当初は「高砂」の名で曳行されていました。
特徴と見どころ:
- 構造:切破風屋根、四輪内板車
- 装飾:
- 下段4隅の丸柱が中段に突き抜け
- 柱先端に青龍刀と4神旗
- 紫鱗紋織り出しの大幕に刺繍された大般若面
- 人形:
- 当初:高砂の翁と媼
- 現在:跳躍する白馬と2人の馬丁
- 音楽:雅楽の越天楽を屋台囃子に使用
歴史的変遷:
- 明和6年(1769年):改造
- 文化13年(1816年):神馬の人形新調、「神馬台」と改称
- 文政13年(1830年):再改造
- その他の修理:安政年間、明治35年(1902年)
逸話:
- 別名「暴れ馬」と呼ばれ、祭り時に隣組とよく騒動があったとされる
仙人台(せんにんたい)
創建:享保3年(1718年)頃 「湯の花」の組から分かれて誕生したとされる古い由緒を持つ屋台です。
特徴と見どころ:
- 構造:唐破風屋根、四輪車内板車
- 建築的価値:
- 最も古い形態を残す屋台
- 唯一唐破風屋根を保持
- 装飾:
- 屋根飾りに極彩色の剣巻龍
- かつては久米の仙人と美女のからくり演技
- 現在の飾り:仙人の像のみを展示
歴史的変遷:
- 明和から安永の始め:現在の仙人台が造られる
- 寛政5年(1793年):記録に「仙人台」の名が登場
- 文政年間:改修
- からくり:明治初期に廃止
工匠:
- 文化改修:古田与兵衛・浅井一之(かずゆき)
行神台(ぎょうじんたい)
創建:享保3年(1718年) 「湯の花」から分かれて創建された由緒ある屋台です。
特徴と見どころ:
- 構造:切破風屋根、四輪内板車
- 祭神:役小角(えんのおずの:役行者)
- 装飾的特徴:
- 中段高欄は玉垣
- 上段高欄の4隅に密教の法具五鈷
- 特別な役割:かつては道開きの屋台として先頭を務める
歴史的変遷:
- 天保2年(1831年):改修
- 明治8年(1875年):大火で一部焼失
- 明治16年(1883年):恵比須台より部品を譲受
- 明治36年(1903年)~昭和26年:休台
- 昭和26年:大修理で50年ぶりに復活
- 近代の修理:昭和43年、昭和59年
由来:
- 地域の開拓者である行者への追慕から命名
- 地域の歴史を象徴する屋台として重要
宝珠台(ほうじゅたい)
創建年代は不詳ですが、安永年間(1772年~1781年)という説があります。
特徴と見どころ:
- 構造:切破風屋根、四輪内板車
- 装飾:
- 屋根飾りに雌雄の大亀一対
- 台名由来の大宝珠3個
- ケヤキ1枚板の台輪は高山屋台中最美とされる
- 歴史的装飾:
- かつては7色に染め分けた宝珠を下段高欄に配置
- 現在は中段と屋根飾りに金銀の宝珠
歴史的変遷:
- 文政11年~12年:大改造
- 明治41年:現在の台形に改修
工匠:
- 文政改造:中洞村喜三郎
- 明治改修:村山民次郎
逸話:
- 屋根の亀が川に入ったという有名な伝説あり
- 「名工の作った亀は水を求めて川に入る」という立て札の逸話
豊明台(ほうめいたい)
創建年代は不詳ですが、当初は「芦刈(あしかり)」という台名で知られていました。
特徴と見どころ:
- 構造:切破風屋根、四輪外御所車
- 歴史的特徴:
- もとは天皇の即位する8角形の高御座(たかみくら)を模した台形
- 明治改修以前は下段・中段とも4隅を切って8角形
- 現在は大幕の部分にその名残を残す
- 装飾:
- 屋根飾りの大鳳凰と宝珠
- 上段の菊花彫刻
- 中段の牡丹彫刻
- 中段の白彫りによる12支の彫刻
- 下段の唐獅子
- 華麗な御所車
歴史的変遷:
- 台名の由来:八幡宮の祭神応神天皇の豊明宮にちなむ
- 天保6年(1835年):改造
- 明治33年~35年:大改修
- 工匠:明治改修時は村山民次郎
鳳凰台(ほうおうたい)
創建年代は不詳ですが、文政元年(1818年)に再興された記録が残っています。
特徴と見どころ:
- 構造:切破風屋根、四輪内板車
- 装飾の特徴:
- 谷越獅子の彫刻:
- 下段にあるケヤキ白彫り
- 高山の屋台彫刻中最大
- 名工谷口与鹿の下絵に基づく
- 与鹿とその弟子浅井一之の合作
- 金具装飾:
- 明治の改修まで3万坪の金具使用
- 精緻な細工と豪華な装飾
- 見送りの特徴:
- 本見送り:柚原双松筆の鳳凰の綴錦織
- 替見送り:西村五雲筆の龍の墨絵
- 谷越獅子の彫刻:
歴史的変遷:
- 文政元年(1818年):再興
- 嘉永4年~7年:改修
- 明治40年~43年:大修理
工匠:
- 嘉永改修:
- 工匠:谷口延恭(のぶやす)
- 彫刻:谷口与鹿・浅井一之
- 明治改修:村山民次郎
11台の屋台が織りなす壮大な祭礼
高山祭の屋台は、単なる山車ではなく、飛騨の匠の技が結集した芸術品として、300年以上の歴史を今に伝えています。11台それぞれが持つ独自の特徴と歴史が、祭礼の場で見事な調和を見せ、訪れる人々を魅了し続けています。
祭礼の幕開けとなる屋台曳き揃えは、秋の高山の空に映える壮大な光景です。9日、10日の日中、布袋台は八幡宮境内に、残る10台は表参道に整然と並びます。飛騨の職人たちが丹精を込めた彫刻や装飾、見送り幕の数々が、一堂に会するこの時間は、まさに野外美術館のような趣きを見せます。見学者は細部にまで行き届いた匠の技に、思わず足を止めて見入ってしまいます。
9日午後に行われる屋台曳き廻しは、秋の高山祭ならではの華やかな行事です。神楽台と鳳凰台は毎年固定で参加し、残る2台は抽選で選ばれます。八幡宮参道北の町内を順行する4台の屋台は、まるで時代絵巻のような荘厳な景観を創り出します。屋台を曳く人々の掛け声、祭囃子の音色が町中に響き渡り、祭りの雰囲気を一層盛り上げます。
八幡宮境内では、9日、10日とも1日2回、布袋台によるからくり奉納が行われます。36本もの糸を操る複雑精緻な技は、飛騨の匠の技術の粋を示すものとして、多くの観客を魅了します。唐子が綾を渡り、布袋様の肩に飛び移る様は、まるで人形に命が宿ったかのような感動を呼び起こします。
祭りの華やかさが最高潮に達するのが、9日夕方からの宵祭です。100個を超える提灯が灯される頃、屋台は幻想的な姿へと装いを変えます。夜の帳が降りた町を練り歩く提灯の光は、幽玄の美を感じさせます。特に、各屋台が屋台蔵へと帰っていく際に歌われる曳き別れ唄「高い山」は、祭りの余韻と哀愁を帯びた情感豊かな風情を醸し出します。
このように11台の屋台は、それぞれが持つ個性を保ちながらも、祭礼という舞台で見事に調和し、高山祭という大きな物語を紡ぎ出します。長い年月をかけて磨き上げられた伝統と技術、そして地域の人々の思いが込められた屋台行事は、現代に生きる私たちに、ものづくりの真髄と祭礼文化の深さを伝え続けているのです。
この壮大な祭礼は、ユネスコ無形文化遺産にも登録され、その価値は国際的にも認められています。飛騨高山の人々が守り継いできた屋台と祭礼の伝統は、次の世代へと確実に受け継がれていくことでしょう。
まとめ:高山祭を最大限楽しむための7つのポイント
- 祭りの流れを把握する 朝の順道場挨拶から夜の宵祭りまで、時間帯によって異なる表情を見せる祭りの流れを理解しておきましょう。
- 見どころの時間配分 屋台曳き揃え、からくり奉納、御神幸行列など、見たい行事の時間帯をしっかり確認しましょう。
- 宵祭りを堪能する 9日夕方からの宵祭りは、100個以上の提灯が灯された幻想的な風景が楽しめます。曳き別れ歌「高い山」も見逃せません。
- 地元の伝統を理解する 飛騨の匠の技と地域の人々の想いが詰まった祭り。しきたりや伝統を理解することで、より深い感動が得られます。
- 天候への備え 10月の高山は朝晩冷え込みます。特に宵祭り観覧時は防寒対策を忘れずに。
- 交通・宿泊の事前確認 祭り期間中は交通規制があり、宿も混雑します。早めの計画が必要です。
- カメラ撮影のコツ 昼の屋台と夜の提灯では撮影設定が大きく異なります。事前の設定確認をお勧めします。
300年以上の歴史を持つ高山祭は、飛騨の人々が守り継いできた貴重な文化遺産です。この記事を参考に、あなただけの高山祭の楽しみ方を見つけてください。